最近のブログ
最近のコメント
各月のブログ
- 2025年12月の一覧
- 2025年11月の一覧
- 2025年10月の一覧
- 2025年9月の一覧
- 2025年8月の一覧
- 2025年7月の一覧
- 2025年6月の一覧
- 2025年5月の一覧
- 2025年4月の一覧
- 2025年3月の一覧
- 2025年2月の一覧
- 2025年1月の一覧
- 2024年12月の一覧
- 2024年11月の一覧
- 2024年10月の一覧
- 2024年9月の一覧
- 2024年8月の一覧
- 2024年7月の一覧
- 2024年6月の一覧
- 2024年5月の一覧
- 2024年4月の一覧
- 2024年3月の一覧
- 2024年2月の一覧
- 2024年1月の一覧
- 2023年12月の一覧
- 2023年11月の一覧
- 2023年10月の一覧
- 2023年9月の一覧
- 2023年8月の一覧
- 2023年7月の一覧
- 2023年6月の一覧
- 2023年5月の一覧
- 2023年4月の一覧
- 2023年3月の一覧
- 2023年2月の一覧
- 2023年1月の一覧
- 2022年12月の一覧
- 2022年11月の一覧
- 2022年10月の一覧
- 2022年9月の一覧
- 2022年8月の一覧
- 2022年7月の一覧
- 2022年6月の一覧
- 2022年5月の一覧
- 2022年4月の一覧
- 2022年3月の一覧
- 2022年2月の一覧
- 2022年1月の一覧
- 2021年12月の一覧
- 2021年11月の一覧
- 2021年10月の一覧
- 2021年9月の一覧
- 2021年8月の一覧
- 2021年7月の一覧
- 2021年6月の一覧
- 2021年5月の一覧
- 2021年4月の一覧
- 2021年3月の一覧
- 2021年2月の一覧
- 2021年1月の一覧
- 2020年12月の一覧
- 2020年11月の一覧
- 2020年10月の一覧
- 2020年9月の一覧
- 2020年8月の一覧
- 2020年7月の一覧
- 2020年6月の一覧
- 2020年5月の一覧
- 2020年4月の一覧
- 2020年3月の一覧
- 2020年2月の一覧
- 2020年1月の一覧
- 2019年12月の一覧
- 2019年11月の一覧
- 2019年10月の一覧
- 2019年9月の一覧
- 2019年8月の一覧
- 2019年7月の一覧
- 2019年6月の一覧
- 2019年5月の一覧
- 2019年4月の一覧
- 2019年3月の一覧
- 2019年2月の一覧
- 2019年1月の一覧
- 2018年12月の一覧
- 2018年11月の一覧
- 2018年10月の一覧
- 2018年9月の一覧
- 2018年8月の一覧
- 2018年7月の一覧
- 2018年6月の一覧
- 2018年5月の一覧
- 2018年4月の一覧
- 2018年3月の一覧
- 2018年2月の一覧
- 2018年1月の一覧
- 2017年12月の一覧
- 2017年11月の一覧
- 2017年10月の一覧
- 2017年9月の一覧
- 2017年8月の一覧
- 2017年7月の一覧
- 2017年6月の一覧
- 2017年5月の一覧
- 2017年4月の一覧
- 2017年3月の一覧
- 2017年2月の一覧
- 2017年1月の一覧
- 2016年12月の一覧
- 2016年11月の一覧
- 2016年10月の一覧
- 2016年9月の一覧
- 2016年8月の一覧
- 2016年7月の一覧
- 2016年6月の一覧
- 2016年5月の一覧
- 2016年4月の一覧
- 2016年3月の一覧
- 2016年2月の一覧
- 2016年1月の一覧
- 2015年12月の一覧
- 2015年11月の一覧
- 2015年10月の一覧
- 2015年9月の一覧
- 2015年8月の一覧
- 2015年7月の一覧
- 2015年6月の一覧
- 2015年5月の一覧
- 2015年4月の一覧
- 2015年3月の一覧
- 2015年2月の一覧
- 2015年1月の一覧
- 2014年12月の一覧
teacupさんのブログ
(一般に公開)
- 万年時計のゼンマイはなぜ真鍮なのか(2) ――弓曳童子2015年02月20日15:13
-
田中久重は江戸時代後期から明治にかけて、最初はからくり師、のちには近代的エンジニアとして活躍しました。万年時計の完成は1851年(嘉永4)。場所は京都。久重は当時、京都四条通烏丸東入ル長刀鉾町に機巧堂という店を経営して、自らの発明品を販売していました。
ちなみに久重は京都に住む前、1835年(天保5)に故郷の九州久留米から大坂へ移住。天保8年の大塩平八郎の乱で焼け出され、伏見へ逃れた後、長刀鉾町に店を開いています。(『田中近江大掾』「田中近江翁年譜」P4~5)
久重は今や東芝の創始者として有名ですが、彼がこうして広く知られるようになったのは、彼が作った弓曳童子というからくり人形の公開がきっかけでした。弓曳童子はそれまで、彼が残した「考案図」(『田中近江大掾』の冒頭に添付)の中に、他のさまざまなからくりと並べて簡単な外観が示されているだけで、実物の存在は一般には知られていませんでした。
弓曳童子は、1989年秋から翌90年春にかけて、江戸からくり復元師の峰崎十五氏の手で修理・調整され、世に出ました。この間の経緯については、上掲写真の峰崎十五著『弓曳童子の再生』(1998年・私家版)に詳しく書かれています。この本には、弓曳童子の構造がよくわかる製作途中のレプリカの写真が豊富に掲載されており、弓曳童子の仕組みを理解したい人にはお勧めです。また峰崎氏は、いわゆる「失敗矢」についても触れています。いつのまにか世の人々の間に、失敗矢を根拠にして「久重は失敗をも演出した」という認識が広まってしまったわけですが、それは誤りであり、峰崎氏が修理の過程で全部の矢を新調した際、たまたまできてしまった「失敗の矢」であることが説明されています。対象をながめる際の“思い込み”が誤った結論を導くことを常に肝に銘じねば、と自戒を込めて思います。
峰崎氏は、本年元日に再放送された放送大学テレビ特別講義「江戸時代のからくり文化」に出演され、失敗矢のことも説明されていましたから、ご覧になった方は、ああ、あの人かと思い出していただけると思います。
久重作とされる弓曳童子は2体現存し、1体はトヨタコレクションとなり、もう1体は久留米市教育委員会が所蔵しています。2体とも動力のゼンマイは真鍮です。
- 時計仕掛けの文化

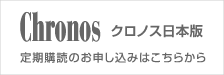

コメント