最近のブログ
最近のコメント
各月のブログ
- 2025年4月の一覧
- 2025年3月の一覧
- 2025年2月の一覧
- 2025年1月の一覧
- 2024年12月の一覧
- 2024年11月の一覧
- 2024年10月の一覧
- 2024年9月の一覧
- 2024年8月の一覧
- 2024年7月の一覧
- 2024年6月の一覧
- 2024年5月の一覧
- 2024年4月の一覧
- 2024年3月の一覧
- 2024年2月の一覧
- 2024年1月の一覧
- 2023年12月の一覧
- 2023年11月の一覧
- 2023年10月の一覧
- 2023年9月の一覧
- 2023年8月の一覧
- 2023年7月の一覧
- 2023年6月の一覧
- 2023年5月の一覧
- 2023年4月の一覧
- 2023年3月の一覧
- 2023年2月の一覧
- 2023年1月の一覧
- 2022年12月の一覧
- 2022年11月の一覧
- 2022年10月の一覧
- 2022年9月の一覧
- 2022年8月の一覧
- 2022年7月の一覧
- 2022年6月の一覧
- 2022年5月の一覧
- 2022年4月の一覧
- 2022年3月の一覧
- 2022年2月の一覧
- 2022年1月の一覧
- 2021年12月の一覧
- 2021年11月の一覧
- 2021年10月の一覧
- 2021年9月の一覧
- 2021年8月の一覧
- 2021年7月の一覧
- 2021年6月の一覧
- 2021年5月の一覧
- 2021年4月の一覧
- 2021年3月の一覧
- 2021年2月の一覧
- 2021年1月の一覧
- 2020年12月の一覧
- 2020年11月の一覧
- 2020年10月の一覧
- 2020年9月の一覧
- 2020年8月の一覧
- 2020年7月の一覧
- 2020年6月の一覧
- 2020年5月の一覧
- 2020年4月の一覧
- 2020年3月の一覧
- 2020年2月の一覧
- 2020年1月の一覧
- 2019年12月の一覧
- 2019年11月の一覧
- 2019年10月の一覧
- 2019年9月の一覧
- 2019年8月の一覧
- 2019年7月の一覧
- 2019年6月の一覧
- 2019年5月の一覧
- 2019年4月の一覧
- 2019年3月の一覧
- 2019年2月の一覧
- 2019年1月の一覧
- 2018年12月の一覧
- 2018年11月の一覧
- 2018年10月の一覧
- 2018年9月の一覧
- 2018年8月の一覧
- 2018年7月の一覧
- 2018年6月の一覧
- 2018年5月の一覧
- 2018年4月の一覧
- 2018年3月の一覧
- 2018年2月の一覧
- 2018年1月の一覧
- 2017年12月の一覧
- 2017年11月の一覧
- 2017年10月の一覧
- 2017年9月の一覧
- 2017年8月の一覧
- 2017年7月の一覧
- 2017年6月の一覧
- 2017年5月の一覧
- 2017年4月の一覧
- 2017年3月の一覧
- 2017年2月の一覧
- 2017年1月の一覧
- 2016年12月の一覧
- 2016年11月の一覧
- 2016年10月の一覧
- 2016年9月の一覧
- 2016年8月の一覧
- 2016年7月の一覧
- 2016年6月の一覧
- 2016年5月の一覧
- 2016年4月の一覧
- 2016年3月の一覧
- 2016年2月の一覧
- 2016年1月の一覧
- 2015年12月の一覧
- 2015年11月の一覧
- 2015年10月の一覧
- 2015年9月の一覧
- 2015年8月の一覧
- 2015年7月の一覧
- 2015年6月の一覧
- 2015年5月の一覧
- 2015年4月の一覧
- 2015年3月の一覧
- 2015年2月の一覧
- 2015年1月の一覧
- 2014年12月の一覧
teacupさんのブログ
(一般に公開)
- 万年時計のゼンマイはなぜ真鍮なのか(4) ――洋時計の利用2015年02月21日13:18
-
前置きが長くなりました。
私が長く疑問に思っていたのは、万年時計の駆動システムでした。
久重は動力として真鍮製のゼンマイを使用し、脱進機は第6面の洋時計の機構を使っています。
洋時計は「フランス製と考えられる時計で、本時計全体のタイムキーパーの役割をもっている」(『復元報告書』P6)ことが明らかになっています。
また、上掲写真の精密工業新聞社編・発行『時計百科事典』(1983年)に菊浦重雄「明治期の時計」という章があり、その「(1)大野規周と田中久重の時計技術」の項に、万年時計の洋時計について「16宝石入り懐中時計」(P547)との説明があります。
これまでさまざまな本に、「万年時計の機構には西洋製の懐中時計が利用されている」ことが述べられてきました。しかしどのようなメーカーの、どのような年代の、どのような機種の懐中時計が用いられているかについて、具体的な説明はありませんでした。『復元報告書』にはその点で以下のような、かなり詳細な説明がなされています。
「古い形状であるが現代の機械時計と同じクラブツース脱進機と5振動のチラネジ付きテンプを持った懐中時計を改造して使っている。」(『復元報告書』P16)
「文字板面は2針短秒針付きであるが、輸入懐中時計を流用したために文字板径が他の表示面と比較して小さくてデザイン的にアンバランスである。右上方半月形のダイアル付きの針は緩急装置、但し彫られている数字と緩急量は一致しない。右下のつまみはスターター、右回転したまま押えているとテンプが止まる。その状態で手を離すとつまみが元へ戻ってテンプ(秒針)が動き出す。右下の黒色のレバーは針合わせ用のクラッチである。下の位置で針回し歯車列が時計から切り離され、上げるとクラッチが入って下中央にある針回しつまみで針合わせできるようになる。外部に出ている操作部と懐中時計部をつなぐ部分の設計には苦心している様子がうかがえる。例えば、下中央のつまみを時計方向に回すと時分針が反時計方向に回って不自然であるが、流用した懐中時計を活かすという制約があったため致し方なかったのであろう。なお追加された針回し機構に使われている歯車は機械で歯割されておりヨーロッパ系の外国製と思われる。
洋時計の動力は、時方の48時間1回転軸に取り付けられているカサ歯車で直交変換される。その後回転方向を変える中間歯車を介して懐中時計のゼンマイを取り払って香箱歯車に直接取り付けた軸の先端の小歯車と噛合う。大カサ歯車(黄銅製)はインボリュート歯形で外国製と思われるが、相手の小カサ歯車(鋼製)のような?歯車は手作りで正常な噛合い部より大きな力がかかるところである。分解調査の結果、大カサ歯車(黄銅製)の歯元に小カサ歯車(鋼製)の歯先が食い込んだ跡が見られた。このまま動かし続ければ遠からずカサ歯車部の噛合い不良で止まるであろう。」(『復元報告書』P17)
さらにこの報告書には、洋時計のムーブメントの写真も、機構の一部を文章の背景にして階調をやや落とした形ではありますが、掲載されています。
私は時計技術に詳しくないので、報告書の説明を読んでも洋時計の写真を見ても、理解できることはそう多くはありませんでした。それで今回、当SNS会員のトキオさんに、報告書のこの部分の文章とムーブメントの写真をお見せしたところ、洋時計部分の懐中時計としての種類、製造されたおおよその年代など、いろいろとお教えいただけました。
トキオさ~ん、万年時計に使用されている洋時計について、ここで再度、解説していただくと助かりま~す。
ちなみに洋時計と真鍮ゼンマイの連結については、次の第5回で触れる予定です。
なお、上掲の『時計百科事典』の内容は、時計の歴史、水晶時計・電気時計・機械時計の各用語集、大名時計博物館の上口愚朗氏の文章「大名時計」(愚朗氏がここで書かれていることは、江戸時代の時計の実物を多数検証された方の知見・考察として、極めて有益です)、さらには「明治・大正時代における我が国時計産業の概観」など多岐にわたっており、700ページ余の労作です。私はこの本に出会ったことで、時計の世界を少しは体系的に理解できるようになりました。
- 時計仕掛けの文化

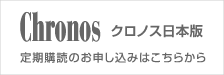

コメント