最近のブログ
最近のコメント
各月のブログ
- 2025年12月の一覧
- 2025年11月の一覧
- 2025年10月の一覧
- 2025年9月の一覧
- 2025年8月の一覧
- 2025年7月の一覧
- 2025年6月の一覧
- 2025年5月の一覧
- 2025年4月の一覧
- 2025年3月の一覧
- 2025年2月の一覧
- 2025年1月の一覧
- 2024年12月の一覧
- 2024年11月の一覧
- 2024年10月の一覧
- 2024年9月の一覧
- 2024年8月の一覧
- 2024年7月の一覧
- 2024年6月の一覧
- 2024年5月の一覧
- 2024年4月の一覧
- 2024年3月の一覧
- 2024年2月の一覧
- 2024年1月の一覧
- 2023年12月の一覧
- 2023年11月の一覧
- 2023年10月の一覧
- 2023年9月の一覧
- 2023年8月の一覧
- 2023年7月の一覧
- 2023年6月の一覧
- 2023年5月の一覧
- 2023年4月の一覧
- 2023年3月の一覧
- 2023年2月の一覧
- 2023年1月の一覧
- 2022年12月の一覧
- 2022年11月の一覧
- 2022年10月の一覧
- 2022年9月の一覧
- 2022年8月の一覧
- 2022年7月の一覧
- 2022年6月の一覧
- 2022年5月の一覧
- 2022年4月の一覧
- 2022年3月の一覧
- 2022年2月の一覧
- 2022年1月の一覧
- 2021年12月の一覧
- 2021年11月の一覧
- 2021年10月の一覧
- 2021年9月の一覧
- 2021年8月の一覧
- 2021年7月の一覧
- 2021年6月の一覧
- 2021年5月の一覧
- 2021年4月の一覧
- 2021年3月の一覧
- 2021年2月の一覧
- 2021年1月の一覧
- 2020年12月の一覧
- 2020年11月の一覧
- 2020年10月の一覧
- 2020年9月の一覧
- 2020年8月の一覧
- 2020年7月の一覧
- 2020年6月の一覧
- 2020年5月の一覧
- 2020年4月の一覧
- 2020年3月の一覧
- 2020年2月の一覧
- 2020年1月の一覧
- 2019年12月の一覧
- 2019年11月の一覧
- 2019年10月の一覧
- 2019年9月の一覧
- 2019年8月の一覧
- 2019年7月の一覧
- 2019年6月の一覧
- 2019年5月の一覧
- 2019年4月の一覧
- 2019年3月の一覧
- 2019年2月の一覧
- 2019年1月の一覧
- 2018年12月の一覧
- 2018年11月の一覧
- 2018年10月の一覧
- 2018年9月の一覧
- 2018年8月の一覧
- 2018年7月の一覧
- 2018年6月の一覧
- 2018年5月の一覧
- 2018年4月の一覧
- 2018年3月の一覧
- 2018年2月の一覧
- 2018年1月の一覧
- 2017年12月の一覧
- 2017年11月の一覧
- 2017年10月の一覧
- 2017年9月の一覧
- 2017年8月の一覧
- 2017年7月の一覧
- 2017年6月の一覧
- 2017年5月の一覧
- 2017年4月の一覧
- 2017年3月の一覧
- 2017年2月の一覧
- 2017年1月の一覧
- 2016年12月の一覧
- 2016年11月の一覧
- 2016年10月の一覧
- 2016年9月の一覧
- 2016年8月の一覧
- 2016年7月の一覧
- 2016年6月の一覧
- 2016年5月の一覧
- 2016年4月の一覧
- 2016年3月の一覧
- 2016年2月の一覧
- 2016年1月の一覧
- 2015年12月の一覧
- 2015年11月の一覧
- 2015年10月の一覧
- 2015年9月の一覧
- 2015年8月の一覧
- 2015年7月の一覧
- 2015年6月の一覧
- 2015年5月の一覧
- 2015年4月の一覧
- 2015年3月の一覧
- 2015年2月の一覧
- 2015年1月の一覧
- 2014年12月の一覧
teacupさんのブログ
(一般に公開)
- 万年時計のゼンマイはなぜ真鍮なのか(9) ――幸野吉郎左衛門2015年02月24日00:11
-
上掲写真は、渡邊庫輔著『長崎の時計師』(1952年・日本時計倶楽部私版)です。
この本は、長崎で活躍した江戸時代の時計技術者の事績について、多数の一次資料の引用によって考察しており、最終的には明治期の長崎の時計産業の発展にまで話が及んでいます。
著者の渡邊庫輔氏は長崎の郷土史家で、芥川龍之介と交流があり、龍之介は渡邊氏のことを「才学の優れている」と高橋邦太郎氏(翻訳家・比較文学研究者)に紹介しています(長崎の時計師P100)。この本は、和時計を研究するうえで極めて貴重かつ有益な参考書だと思います。
『長崎の時計師』は――
「享保十四酉(一七二九)年、長崎の時計師幸野吉郎左衛門は、将軍家の香箱時計を修繕した。」
――という一文から始まっています。この件を含めた幸野家の記録が残っており、渡邊氏はこの記録を詳細に引用して論じています。
「香箱時計」とはゼンマイ時計のことで、幸野家の記録に「阿蘭陀仕懸之通、昼夜長短なしにて」(同書P2)とあるので、この将軍家の香箱時計は西洋製のまま、不定時法に改造されることなく使用され、故障したと考えられます。
そしてさらに以下のような、この時計の修理見積もりが引用されています。
「一(※)太皷之内之大せんまい、全躰短く御座候故、車之めくりニたり不申候。殊ニせんまい弐筋入居申候故不宣候間、是又新規ニ拵直し不申候へハ不罷成候。勿論、弐筋ニ而ハ不宣候間、新規ニ拵申候ハ壱筋ニ仕候。則絵図差上候。」(同書P2)
※この「一」とは、項目を立てる意味の「一(ひとつ)」です(teacup注)。
つまり吉郎左衛門は、「ドラムの中に入っている大型ゼンマイが、全体として短いので、歯車を回転させるのに足りません。とりわけ、ゼンマイを二筋入れた形になっていてよくないので、新たに作り直さないといけません。もちろん二筋ではよくないので、新規に作るのは一筋のゼンマイにいたします。ご説明のための図をお渡しいたします。」と言っているのです。この洋時計のオリジナルゼンマイと同様の、鋼のゼンマイを作って修理した、と読めます。
吉郎左衛門は、刀鍛冶として高い技術を持っていたことが、記録として残っています(同書P5~6)。さらに彼は、将軍家の香箱時計を修理した翌年の享保15年から、長崎の出島に出入りすることを許されています(同書P1)。
吉郎左衛門は、その優れた鍛冶能力によって、時計に使用できる鋼のゼンマイを作ることに成功した。あるいは、長崎という地の利を活かして出島のオランダ人から間接、直接に西洋のゼンマイを輸入し、時計の修理や製作に使用した。どちらの可能性もあると思います。
享保年間つまり江戸中期に、もし幸野吉郎左衛門が鋼のゼンマイの国産化に成功していたとすると、その技術が他に広がらないまま、100年以上のちの久重の万年時計製作に至ったのでしょうか。
- 時計仕掛けの文化
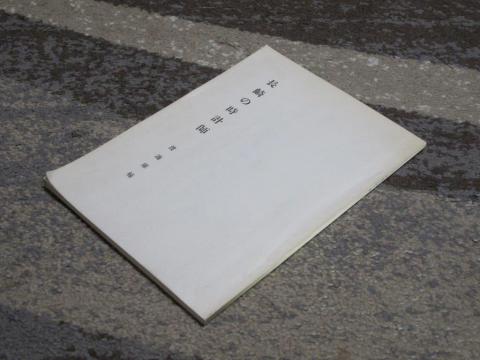
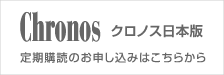

コメント