最近のブログ
最近のコメント
各月のブログ
- 2025年4月の一覧
- 2025年3月の一覧
- 2025年2月の一覧
- 2025年1月の一覧
- 2024年12月の一覧
- 2024年11月の一覧
- 2024年10月の一覧
- 2024年9月の一覧
- 2024年8月の一覧
- 2024年7月の一覧
- 2024年6月の一覧
- 2024年5月の一覧
- 2024年4月の一覧
- 2024年3月の一覧
- 2024年2月の一覧
- 2024年1月の一覧
- 2023年12月の一覧
- 2023年11月の一覧
- 2023年10月の一覧
- 2023年9月の一覧
- 2023年8月の一覧
- 2023年7月の一覧
- 2023年6月の一覧
- 2023年5月の一覧
- 2023年4月の一覧
- 2023年3月の一覧
- 2023年2月の一覧
- 2023年1月の一覧
- 2022年12月の一覧
- 2022年11月の一覧
- 2022年10月の一覧
- 2022年9月の一覧
- 2022年8月の一覧
- 2022年7月の一覧
- 2022年6月の一覧
- 2022年5月の一覧
- 2022年4月の一覧
- 2022年3月の一覧
- 2022年2月の一覧
- 2022年1月の一覧
- 2021年12月の一覧
- 2021年11月の一覧
- 2021年10月の一覧
- 2021年9月の一覧
- 2021年8月の一覧
- 2021年7月の一覧
- 2021年6月の一覧
- 2021年5月の一覧
- 2021年4月の一覧
- 2021年3月の一覧
- 2021年2月の一覧
- 2021年1月の一覧
- 2020年12月の一覧
- 2020年11月の一覧
- 2020年10月の一覧
- 2020年9月の一覧
- 2020年8月の一覧
- 2020年7月の一覧
- 2020年6月の一覧
- 2020年5月の一覧
- 2020年4月の一覧
- 2020年3月の一覧
- 2020年2月の一覧
- 2020年1月の一覧
- 2019年12月の一覧
- 2019年11月の一覧
- 2019年10月の一覧
- 2019年9月の一覧
- 2019年8月の一覧
- 2019年7月の一覧
- 2019年6月の一覧
- 2019年5月の一覧
- 2019年4月の一覧
- 2019年3月の一覧
- 2019年2月の一覧
- 2019年1月の一覧
- 2018年12月の一覧
- 2018年11月の一覧
- 2018年10月の一覧
- 2018年9月の一覧
- 2018年8月の一覧
- 2018年7月の一覧
- 2018年6月の一覧
- 2018年5月の一覧
- 2018年4月の一覧
- 2018年3月の一覧
- 2018年2月の一覧
- 2018年1月の一覧
- 2017年12月の一覧
- 2017年11月の一覧
- 2017年10月の一覧
- 2017年9月の一覧
- 2017年8月の一覧
- 2017年7月の一覧
- 2017年6月の一覧
- 2017年5月の一覧
- 2017年4月の一覧
- 2017年3月の一覧
- 2017年2月の一覧
- 2017年1月の一覧
- 2016年12月の一覧
- 2016年11月の一覧
- 2016年10月の一覧
- 2016年9月の一覧
- 2016年8月の一覧
- 2016年7月の一覧
- 2016年6月の一覧
- 2016年5月の一覧
- 2016年4月の一覧
- 2016年3月の一覧
- 2016年2月の一覧
- 2016年1月の一覧
- 2015年12月の一覧
- 2015年11月の一覧
- 2015年10月の一覧
- 2015年9月の一覧
- 2015年8月の一覧
- 2015年7月の一覧
- 2015年6月の一覧
- 2015年5月の一覧
- 2015年4月の一覧
- 2015年3月の一覧
- 2015年2月の一覧
- 2015年1月の一覧
- 2014年12月の一覧
teacupさんのブログ
(一般に公開)
- 万年時計のゼンマイはなぜ真鍮なのか(10) ――幸野吉郎七2015年02月24日13:25
-
『長崎の時計師』によれば、吉郎左衛門は延享5年(1748)に没し、翌年になって息子の吉郎七が御時計師を継いでいます(同書P13)。
そして吉郎七は宝暦八年(1758)に、枕形御時計、丸形御時計、時打香盒御時計、印籠形御時計、六分香盒御時計、錫箱入香盒御時計という、6個の時計を修理した記録があり、その記録の最後は「右六餝之御時計、宝暦八寅年、御修覆披仰付仕立差上申候」(同書P14)と結ばれています。これらの時計がどのようなものであったか、具体的なことは『長崎の時計師』には述べられていません。
塚田泰三郎著『和時計』のP32には、吉郎七が修理した「時打香盒御時計」を、「今でいう引き打ち、あるいは押し打ちの懐中時計のことであろう。両がわの懐中時計の側面に出ているダボを下に下げると、(あるいは内側に押す)その時の時刻を何時何分と鐘の音で報ずるものである。」と述べています。つまり、西洋製のミニッツリピーターであろうとの推測です。
山口隆二著『日本の時計』には、初版でも改訂版でも「日本ではゼンマイを動力とする枕時計が製作されるようになったのは十八世紀末から十九世紀の初にいたる頃である。」(初版、改訂版ともにP210)と書かれています(第8回で触れた1796年刊の機巧図彙には、目次のみで作り方は掲載されていませんが、枕時計が項目としてあげられています)。
吉郎七が修理した時計はすべて西洋製で、枕形御時計はゼンマイ動力の置時計、時打香盒御時計はミニッツリピーター、印籠形御時計は懐中時計だったのでしょうか。いや、すくなくとも枕形御時計は、和時計の一種の枕時計で、それを修理したのでしょうか。
宝暦10年、吉郎七はさらに8台の時計を修理したことが「吉郎七書上勤方書付」に記されています(『長崎の時計師』P13)。それらの時計は、三寸櫓御時計、枕形御時計、時打香盒御時計、印籠形御時計、六分香盒御時計、錫箱入御時計、丸形根付御時計ならびに、二ノ御丸御用の三寸櫓御時計で、「右八餝、江戸表へ参上仕候節、(一字難読※)シ直シ被仰付早速相直シ差上申候」(同書P15)とあります。
※この「一字難読」は、著者渡邊庫輔氏の注意書きで、原著には実際の難読文字も記載されています。(teacup注)
文書中の櫓時計や香盒時計の頭に付けられている「三寸(約90㎜)」とか「六分(約18㎜)」といった寸法が何を意味するのかわかりませんが、櫓御時計は和時計だろうと思うのです。とすれば、列記してあるうちのどれが和時計でどれが洋時計か、区別をつけるのは一層困難です。
- 時計仕掛けの文化

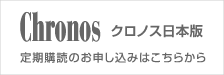

コメント