最近のブログ
最近のコメント
各月のブログ
- 2025年12月の一覧
- 2025年11月の一覧
- 2025年10月の一覧
- 2025年9月の一覧
- 2025年8月の一覧
- 2025年7月の一覧
- 2025年6月の一覧
- 2025年5月の一覧
- 2025年4月の一覧
- 2025年3月の一覧
- 2025年2月の一覧
- 2025年1月の一覧
- 2024年12月の一覧
- 2024年11月の一覧
- 2024年10月の一覧
- 2024年9月の一覧
- 2024年8月の一覧
- 2024年7月の一覧
- 2024年6月の一覧
- 2024年5月の一覧
- 2024年4月の一覧
- 2024年3月の一覧
- 2024年2月の一覧
- 2024年1月の一覧
- 2023年12月の一覧
- 2023年11月の一覧
- 2023年10月の一覧
- 2023年9月の一覧
- 2023年8月の一覧
- 2023年7月の一覧
- 2023年6月の一覧
- 2023年5月の一覧
- 2023年4月の一覧
- 2023年3月の一覧
- 2023年2月の一覧
- 2023年1月の一覧
- 2022年12月の一覧
- 2022年11月の一覧
- 2022年10月の一覧
- 2022年9月の一覧
- 2022年8月の一覧
- 2022年7月の一覧
- 2022年6月の一覧
- 2022年5月の一覧
- 2022年4月の一覧
- 2022年3月の一覧
- 2022年2月の一覧
- 2022年1月の一覧
- 2021年12月の一覧
- 2021年11月の一覧
- 2021年10月の一覧
- 2021年9月の一覧
- 2021年8月の一覧
- 2021年7月の一覧
- 2021年6月の一覧
- 2021年5月の一覧
- 2021年4月の一覧
- 2021年3月の一覧
- 2021年2月の一覧
- 2021年1月の一覧
- 2020年12月の一覧
- 2020年11月の一覧
- 2020年10月の一覧
- 2020年9月の一覧
- 2020年8月の一覧
- 2020年7月の一覧
- 2020年6月の一覧
- 2020年5月の一覧
- 2020年4月の一覧
- 2020年3月の一覧
- 2020年2月の一覧
- 2020年1月の一覧
- 2019年12月の一覧
- 2019年11月の一覧
- 2019年10月の一覧
- 2019年9月の一覧
- 2019年8月の一覧
- 2019年7月の一覧
- 2019年6月の一覧
- 2019年5月の一覧
- 2019年4月の一覧
- 2019年3月の一覧
- 2019年2月の一覧
- 2019年1月の一覧
- 2018年12月の一覧
- 2018年11月の一覧
- 2018年10月の一覧
- 2018年9月の一覧
- 2018年8月の一覧
- 2018年7月の一覧
- 2018年6月の一覧
- 2018年5月の一覧
- 2018年4月の一覧
- 2018年3月の一覧
- 2018年2月の一覧
- 2018年1月の一覧
- 2017年12月の一覧
- 2017年11月の一覧
- 2017年10月の一覧
- 2017年9月の一覧
- 2017年8月の一覧
- 2017年7月の一覧
- 2017年6月の一覧
- 2017年5月の一覧
- 2017年4月の一覧
- 2017年3月の一覧
- 2017年2月の一覧
- 2017年1月の一覧
- 2016年12月の一覧
- 2016年11月の一覧
- 2016年10月の一覧
- 2016年9月の一覧
- 2016年8月の一覧
- 2016年7月の一覧
- 2016年6月の一覧
- 2016年5月の一覧
- 2016年4月の一覧
- 2016年3月の一覧
- 2016年2月の一覧
- 2016年1月の一覧
- 2015年12月の一覧
- 2015年11月の一覧
- 2015年10月の一覧
- 2015年9月の一覧
- 2015年8月の一覧
- 2015年7月の一覧
- 2015年6月の一覧
- 2015年5月の一覧
- 2015年4月の一覧
- 2015年3月の一覧
- 2015年2月の一覧
- 2015年1月の一覧
- 2014年12月の一覧
teacupさんのブログ
(一般に公開)
- 万年時計のゼンマイはなぜ真鍮なのか(11) ――西洋人の思惑2015年02月24日19:28
-
上口愚朗氏は、「日本時刻時計に改造された外国製の時計はたくさんある。これを私は和前時計と呼んでいる。(古い時計箱にそう記してあるのを持っている)」とし、和前時計とは「エト文字盤と歯車の一部を日本時刻に改造した外国時計のこと」と述べています(『時計百科事典』P502)。言うまでもありませんが、日本時刻とは不定時法のことです。
ちなみに上口氏の文章の中に挿入されている和前時計の写真は、ゼンマイ駆動の立派な置き時計で、写真が不鮮明でわかりにくいのですが、ローマ数字の文字盤の内側に割駒式のエト文字板がはめこまれているようで、時針も和時計のデザインに見えます。
となると江戸時代には、洋時計、和前時計、和時計が、混在していたことになります。当時の将軍家や大名家ではそうした状況はあたりまえのことで、とくに説明する必要などなかったから、幸野家の文書にもそれぞれの時計について細かく内容を記載しなかった、ということでしょうか。
西洋人は戦国時代から江戸時代にかけて、日本の時の権力者たちに取り入るため、多くの献上品を用意しました。なかでも機械時計は、権力者の歓心を買うための献上品として多用されたようです。日本に西洋の機械時計がもたらされた最古の記録は、フランシスコ・ザビエルが山口の戦国大名大内義隆に1551年に献上した件に関するもので、大内義隆が滅ぼされた直後に、大内家の菩提寺の住持である日継須益によって書かれたとされる『大内義隆記』と、ザビエルが本国に送った書簡など、日本側、西洋側、双方の記録が残っています。
ちなみに上掲写真は、山口市の山口ザビエル記念聖堂にあるザビエル像です。
江戸時代には、長崎出島のオランダ商館長が江戸の将軍へ献上品を持って挨拶に行くのが恒例となり、その参府の回数がどれくらいにのぼったかと言えば、片桐一男著『京のオランダ人 阿蘭陀宿海老屋の実態』(1998年・吉川弘文館)P12に、「嘉永3年(1850)度分まで実に166回を数える。」とあります。
また塚田泰三郎著『和時計』P31には、「アルフレド・シャピュイ氏は「時計とレンズ」誌の滞日蘭人と時計の中で次のように書いている。」との書き出しで、ハーグの国立公文書館に保存されている出島蘭館文書を土台としたシャピュイの考察を、日本語訳で掲載しているのですが、その訳の中に「文献によると、時計は常に献上品目に加えられていたことを証明している。即ち、長きにわたって時計は皇帝(将軍)及び世継ぎに限り贈呈されていたのであった。」との文章があります。
オランダ商館長が166回の参府のたびに、将軍を喜ばせようと機械時計を持参したとすれば、江戸城にはかなりの数の、各種・各時代の洋時計が集まったことになります。
江戸城にはさまざまな時計が、数百年の間、入れ替わり立ち替わり鎮座したことでしょう。現在、久能山東照宮に所蔵されているハンス・デ・エヴァロの時計のように、オリジナルの状態で大切に動かされた洋時計。不定時法に改造され、和前時計として日々使用された洋時計。日本の時計師たちが開発し、改良し、多様に発展させた和時計。それらの時計のどれもが、一旦不具合を生じたときには、幸野吉郎左右衛門ら優秀な時計師たちに「修理せよ」との御下命がくだったと思われます。
それにしても、修理を依頼するほど必要とされていたそれらの時計は、江戸城で日々、どのように動かされ、管理されていたのでしょうか。
- 時計仕掛けの文化

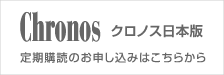

コメント