| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
最近のブログ
最近のコメント
各月のブログ
- 2025年12月の一覧
- 2025年11月の一覧
- 2025年10月の一覧
- 2025年9月の一覧
- 2025年8月の一覧
- 2025年7月の一覧
- 2025年6月の一覧
- 2025年5月の一覧
- 2025年4月の一覧
- 2025年3月の一覧
- 2025年2月の一覧
- 2025年1月の一覧
- 2024年12月の一覧
- 2024年11月の一覧
- 2024年10月の一覧
- 2024年9月の一覧
- 2024年8月の一覧
- 2024年7月の一覧
- 2024年6月の一覧
- 2024年5月の一覧
- 2024年4月の一覧
- 2024年3月の一覧
- 2024年2月の一覧
- 2024年1月の一覧
- 2023年12月の一覧
- 2023年11月の一覧
- 2023年10月の一覧
- 2023年9月の一覧
- 2023年8月の一覧
- 2023年7月の一覧
- 2023年6月の一覧
- 2023年5月の一覧
- 2023年4月の一覧
- 2023年3月の一覧
- 2023年2月の一覧
- 2023年1月の一覧
- 2022年12月の一覧
- 2022年11月の一覧
- 2022年10月の一覧
- 2022年9月の一覧
- 2022年8月の一覧
- 2022年7月の一覧
- 2022年6月の一覧
- 2022年5月の一覧
- 2022年4月の一覧
- 2022年3月の一覧
- 2022年2月の一覧
- 2022年1月の一覧
- 2021年12月の一覧
- 2021年11月の一覧
- 2021年10月の一覧
- 2021年9月の一覧
- 2021年8月の一覧
- 2021年7月の一覧
- 2021年6月の一覧
- 2021年5月の一覧
- 2021年4月の一覧
- 2021年3月の一覧
- 2021年2月の一覧
- 2021年1月の一覧
- 2020年12月の一覧
- 2020年11月の一覧
- 2020年10月の一覧
- 2020年9月の一覧
- 2020年8月の一覧
- 2020年7月の一覧
- 2020年6月の一覧
- 2020年5月の一覧
- 2020年4月の一覧
- 2020年3月の一覧
- 2020年2月の一覧
- 2020年1月の一覧
- 2019年12月の一覧
- 2019年11月の一覧
- 2019年10月の一覧
- 2019年9月の一覧
- 2019年8月の一覧
- 2019年7月の一覧
- 2019年6月の一覧
- 2019年5月の一覧
- 2019年4月の一覧
- 2019年3月の一覧
- 2019年2月の一覧
- 2019年1月の一覧
- 2018年12月の一覧
- 2018年11月の一覧
- 2018年10月の一覧
- 2018年9月の一覧
- 2018年8月の一覧
- 2018年7月の一覧
- 2018年6月の一覧
- 2018年5月の一覧
- 2018年4月の一覧
- 2018年3月の一覧
- 2018年2月の一覧
- 2018年1月の一覧
- 2017年12月の一覧
- 2017年11月の一覧
- 2017年10月の一覧
- 2017年9月の一覧
- 2017年8月の一覧
- 2017年7月の一覧
- 2017年6月の一覧
- 2017年5月の一覧
- 2017年4月の一覧
- 2017年3月の一覧
- 2017年2月の一覧
- 2017年1月の一覧
- 2016年12月の一覧
- 2016年11月の一覧
- 2016年10月の一覧
- 2016年9月の一覧
- 2016年8月の一覧
- 2016年7月の一覧
- 2016年6月の一覧
- 2016年5月の一覧
- 2016年4月の一覧
- 2016年3月の一覧
- 2016年2月の一覧
- 2016年1月の一覧
- 2015年12月の一覧
- 2015年11月の一覧
- 2015年10月の一覧
- 2015年9月の一覧
- 2015年8月の一覧
- 2015年7月の一覧
- 2015年6月の一覧
- 2015年5月の一覧
- 2015年4月の一覧
- 2015年3月の一覧
- 2015年2月の一覧
- 2015年1月の一覧
- 2014年12月の一覧
teacupさんのブログ
(一般に公開)
- 万年時計のゼンマイはなぜ真鍮なのか(補習1)2015年03月15日10:27
-
このシリーズ第3回の末尾に――
報告書『万年時計復元・複製プロジェクト』の関係者による論文が発表されており、日本語の論文はネットで参照できず、英語の論文は参照できる旨、述べました。
それが本日、日本語の論文も「万年時計の機構解明 第1報」および「第2報」として、ネットの以下のアドレスで参照可能なのがわかりました。ご興味がある方はご覧ください。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaic1979/73/729/73...
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaic1979/73/729/73...
今後も、もし万年時計に関連して何か、思いつきなり発見があれば、「補習」としてアップしたいと思います。
ちなみに上掲写真は万年時計には何の関係もありませんが、ウェブクロノスの会員の皆さんにはご興味があるかとも思い、アップします。書名等のデータは以下のとおりです。
George Daniels著『Watchmaking』(Drawing by David Penney 1981年刊 Sotheby Publications)全416ページ。
この本はたしか30年ほど前、ロンドンのKeith Harding のショップ兼工房を訪れた時に購入したものだと思います。購入はしたものの、中身は読んでおりません。参考になるかもと思って購入し、ざっと目を通したあと読まないままになっている本や雑誌は私、いろいろあります。
そうやって積んでおいたものを、のちに「あ、あれが参考になるかも」と思って読んで、すごい発見(私にとって、ですよ)をしたことが何度もあります。今もそうした発見は続いていて、書籍とその著者、雑誌とその記事の作者に感謝するわけです。
この本を買ったKeith Hardingは、「オルゴールのロールス・ロイス」と言われるNicole Frere のリストアのスペシャリストとして知られていました。Keith Hardingは最近、亡くなりました。彼とは何度か手紙のやりとりをしたり、国際電話で話をしたりしましたが、会ったのはこのとき1度きりでした。工房内部の写真を撮らせてもらい、共同経営者のCliff Burnettにいろいろ話を聞いたことを思い出します。
- 時計仕掛けの文化

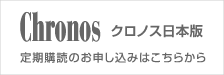

コメント