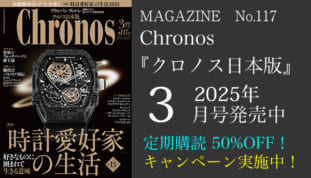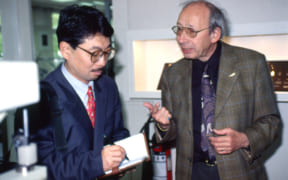30年以上にわたって時計業界を取材してきたジャーナリスト菅原茂氏による、webChronosでの連載「スイス時間旅行−追想の90年代」。第5回は、ラ・ショー・ド・フォンを代表するブランド、エベルを取材した記録だ。3度にわたって訪れた本社で、菅原氏がとりわけ強く印象に残った言葉とは? なお、この地で出合ったという“謎多きクロノグラフ”も必見だ。

Text by Shigeru Sugawara
[2025年2月6日公開記事]
時計産業都市ラ・ショー・ド・フォンから、エベルを振り返る
スイスの時計産業は、ジュネーブやジュラ山脈の山中に開けた平地で発展した。ラ・ショー・ド・フォンもそのひとつ。1990年代半ばから2000年代始めの頃は、バーゼルとジュネーブで開催された時計展示会の期間中に宿泊や取材でよく訪れた。18世紀末の大火で焼失した街を時計産業都市として計画的に整備して復興を遂げたことからユネスコ世界遺産に登録されているが、今や近郊にはカルティエをはじめいくつもの工場が立ち並び、すっかり近代的な時計産業都市へと生まれ変わった。1990年代のラ・ショー・ド・フォンを代表するブランドとなると、ジラール・ペルゴとエベルが双璧だろう。ジラール・ペルゴは1852年、エベルは1911年にそれぞれここに工場を構えた。今回はまずエベルを振り返る。
時の建築家とクロノグラフ
エベルについては銀座和光が代理店だった時代から知っていたが、ジュエリー誌の編集に携わっていた当時はハイソな顧客向けの洒落た時計というイメージでとらえていた。欧米ではロレックスを凌ぐ人気を誇り、著名人に愛用者も多かった。1990年代は輸入商社の日本シイベルヘグナー(現DKSH)が扱い、日本における認知度もぐんと高まった。エベルといえば、ブランドが掲げる「THE ARCHITECTS OF TIME 時の建築家」が有名だ。スポーティーエレガンスをコンセプトにした、モダンでラグジュアリーな時計を得意とするエベルの世界観を伝えるのが、簡潔ながらも意味深長なこの言葉なのだった。
手元にあった古い資料を参照すると、あの滑らかな曲線にビスのアクセントを配した、ひと目で分かるアイコニックなデザインは、1977年の「スポーツクラシック」に始まり、以下の機械式クロノグラフに受け継がれていたことが分かる。すなわち「スポーツ クロノグラフ」(1982年、エル・プリメロCal.400)、「パーペチュアルカレンダー クロノグラフ」(1983年※、エル・プリメロがベースのCal.136)、「ル・モデュロール」(1995年、レマニア共同開発Cal.137)である。こうして振り返ると、世界でクォーツが全盛を迎え、機械式時計、ましてや機械式クロノグラフがふるわなかった1980年代に、スタイリッシュなデザインによるこれらのモデルそれを発表していたエベルは、スイス時計産業では異色の存在だったと言えるだろう。(※発売は1984年)


エベル本社を3度にわたって取材する
そんなエベル(バーゼル見本市や本社では、EBELをイーベルと発音する者が多い)の時計づくりをこの目で見てみたいと思い、1994年春に工場を初めて訪れた。バーゼル94の会場取材を終え、ラ・ショー・ド・フォン名物の国際時計博物館の見学を終えた翌日のことだった。本社工場でムーブメントやユニークな形状のケースについて取材させてほしいと申し出ると、案内者は「撮影はこちらの許可したところだけを厳守してほしい」と言う。エベルはパリの有名宝飾ブランドも手掛けていた。フランコ・コローニの「TANK」に関する著書にもはっきり書いてあるように、1990年代の終わりまでカルティエ向けのクォーツムーブメントを作っていたのである。もちろんそうした現場は見せなかったわけだが、エベルの製造ラインでも結局撮影はできず、広報画像(当時は35mmポジフィルム)や資料をもらうことになった。
ヴィラ・テュルク

工場見学を終えて、社屋近くの建物へと案内された。かの有名な建築家ル・コルビュジェの設計による1910年代の「ヴィラ・テュルク」である。それは「時の建築家」のエベルにとって象徴的な建物だ。エベルはラ・ショー・ド・フォンのランドマークのひとつに数えられるこの瀟洒な歴史的建造物を1986年に購入し、プライベートなゲストハウスとして利用していた。筆者は1995年、1996年と2回もヴィラ・テュルクに宿泊する機会に恵まれた。優雅なヴィラの中でゆったり過ごした時間はとりわけ格別だった。
クロノグラフムーブメントの刷新
さて1996年、エベルの本社訪問3回目は、バーゼル95で発表された最新クロノグラフ「ル・モデュロール」に搭載された新型ムーブメントの徹底取材が目的。対応していただいたのは、技術部のフランソワ・ジラルデとジャン・クロード・ドラプレスの両氏、そしてエベル・ウォッチの造形美を創作するデザイナーのベン・ショダー氏。先に述べたように、1980年代にさかのぼるエベル「スポーツ クロノグラフ」の搭載ムーブメントは、ゼニスのエル・プリメロCal.400を自社仕様にアレンジ。同時代のロレックス「デイトナ」はCal.400を改造したものだから、似たもの同士と言えなくもない。しかし、エベルは、1960年代に設計されたエル・プリメロに残る古い構造に満足できず、何年も前から新型ムーブメントの開発に取り組んでいたという。
ジラルデ氏の発言で今でも強く印象に残っているのは「コラムホイールは時代遅れだ!」という言葉である(今ならどうだろう?)。彼は、パーツの徹底した削減と統合により、コンパクトで高性能のクロノグラフムーブメントCal.137を完成させた胸を張る。さらにCOSC認定クロノメーターの高精度も特徴になった。ちなみにレマニアと共同開発したとの説明もあったことを加えておく。当時の自動巻きクロノグラフムーブメントとしては非常に優秀なこのCal.137を搭載し、時計全体のデザインをさらに洗練させた「ル・モデュロール」は、その後「1911クロノグラフ」と名を変えて人気を博したわけだが、ブランドのあれやこれやのオーナーシップの変転に続いて、2012年にムーブメントのCal.137がユリスナルダンに売却されたと知って愕然とした。あのクロノグラフが終わったとは!
謎多きクロノグラフ「De Berccy」との出合い
最後にラ・ショー・ド・フォンの思い出として、おまけをひとつ加えよう。1996年にエベルを取材したときのエピソードである。街の裏通りを散歩中に見つけた小さな店で出会ったクロノグラフだ。陶器やブリキのおもちゃが並ぶ中に飾られた3本のクロノグラフは、ケースやダイアルのディテールに凝った趣味性豊かなデザインで、シースルーバックから見える自動巻きムーブメントにも彫金と金メッキ仕上げが施され、時計好きを魅了するなかなかの演出に目が留まった。さすがに時計産業都市、街にたくさんの存在する工房を利用して好みのパーツを組み上げれば、こんな特別感のある時計が作れるのかもしれない。そう考えると、このクロノグラフはラ・ショー・ド・フォンの縮図と言えるのではないか。

店の奥の作業台で作っているのは年配の男性。名刺の名はベルツキと読むのか、まあそんな感じで、時計のスペシャリストという肩書が添えてあった。後にバーゼルでダービー&シャルデンブランを取材していたときに判明したのだが、この謎の時計師さんは、ダービーのマスターウォッチメーカーなのだった。そういえば金メッキ仕上げのムーブメントはダービーによく似ている。エベルで最新のクロノグラフを見た後に、まったく対照的なヴィンテージスタイルのクロノグラフもいいなと思い、さっそく購入を決意。値段は900スイスフラン(当時のレートで8万円ほど)だから、コスパ抜群というところだろう。いい買い物になった思い出のクロノグラフは、あれから30年が経った今でも現役。たまに着けて楽しんでいる。


菅原茂氏のプロフィール

1954年生まれ。時計ジャーナリスト。1980年代にファッション誌やジュエリー専門誌でフランスやイタリアを取材。1990年代より時計に専念し、スイスで毎年開催されていた時計の見本市を25年以上にわたって取材。『クロノス日本版』などの時計専門誌や一般誌に多数の記事を執筆・発表。時計専門書の翻訳も手掛ける。