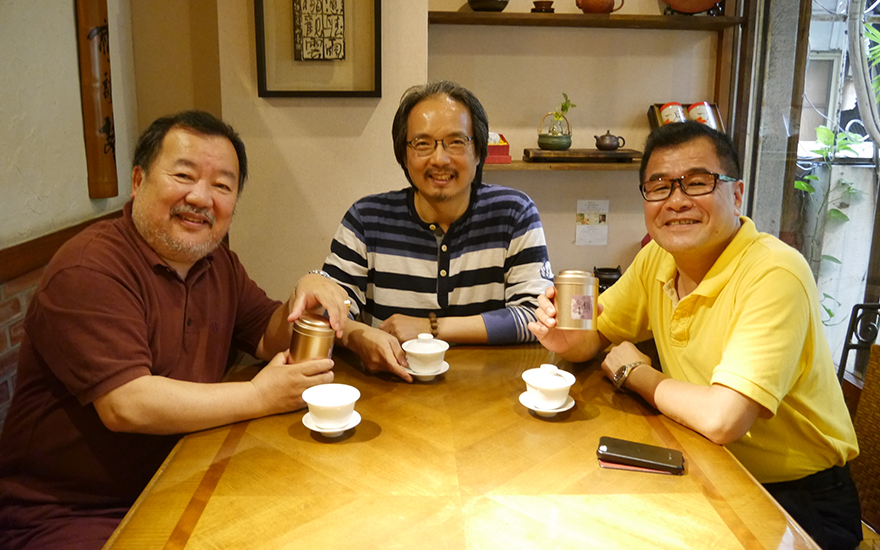
松山猛・著『ちゃあい』より(1995年、風塵社刊)
茶壺
中国茶を飲み慣れると、その道具が気になるのは当然のことだ。特に茶壺=ツアフーと呼ばれる急須だけは、茶の味や香りの出方を決定するだけに、気を配りすぎるということはない。
横浜の中華街あたりに行くと、各種の中国茶具を見つけることができるが、たいていは紫砂(朱泥)を焼いた、我が国の万古焼風のもの。それもそのはずで、万古焼はこれら中国の朱泥器を模した江戸期の国産品だったのだ。
焼き物の国中国を代表するのは、景徳鎮の磁器だが、広大な国だけに別の地方にも、おもしろい土がたくさんとれる。
上海の西、太湖の近く、紫砂器で有名な宜興の町があり、昔もいまもここが茶壺の名産地とされている。
もともと喫茶と縁の深い禅寺で、手先の器用なお坊さんが、手すさびにひねり出したのがはじまりとされているが、これは茶をいれるのに、実に合理的な道具として、すぐに広まっていく。
時代と共に茶のいれ方が変わり、粉末にした抹茶や、茶葉を煮る煮茶の時代が終わって、熱湯で蒸すようにいれる、今風の煎茶法が確立すると、茶壺はなくてはならぬ道具となった。
その多くは赤レンガ色の朱泥だが、緑色や黄褐色など土の色彩は豊かな変化を見せる。なかには砂粒をねり込んだ、梨皮風の物や、ねり込み手、多色づかいの物もある。
また詩文を刻(ほ)ったり、茶壺自体を果物や竹に見立てた物、動物のかたちを模した物など、まさに千変万化のおもしろさがあって、中国の造形の妙にとりつかれてしまうと、実用品以外にもあれこれ集めてしまいたくなってくるのだ。
科学的にとらえているわけではないのだが、この朱泥器は滑らかなようでいて実は細かな穴がいっぱいあるらしい。
そこに茶の成分がしみ込んで、より良い茶壺となり、えも言われぬ茶を出すのだと昔から言われている。










