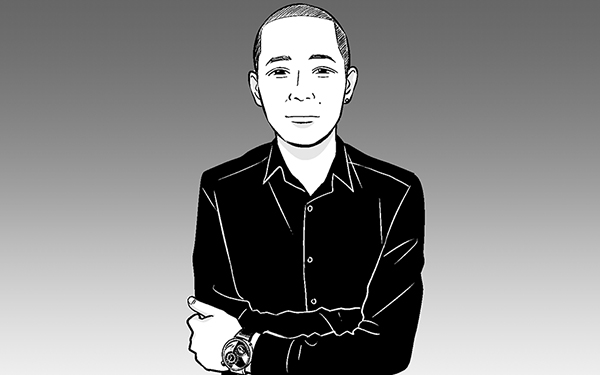2020年2月掲載記事
時計の賢人たちの原点となった最初の時計、そして彼らが最後に手に入れたいと願う時計、いわゆる「上がり時計」とは一体何だろうか? 本連載では、時計業界におけるキーパーソンに取材を行い、その答えから彼らの時計人生や哲学を垣間見ていこうというものである。
今回話を聞いたのは、作家の松山猛氏だ。松山氏が挙げた原点時計はグリュエンのトノー型アンティークウォッチ、「上がり時計」はF.P.ジュルヌである。その言葉を聞いてみよう。
松山猛
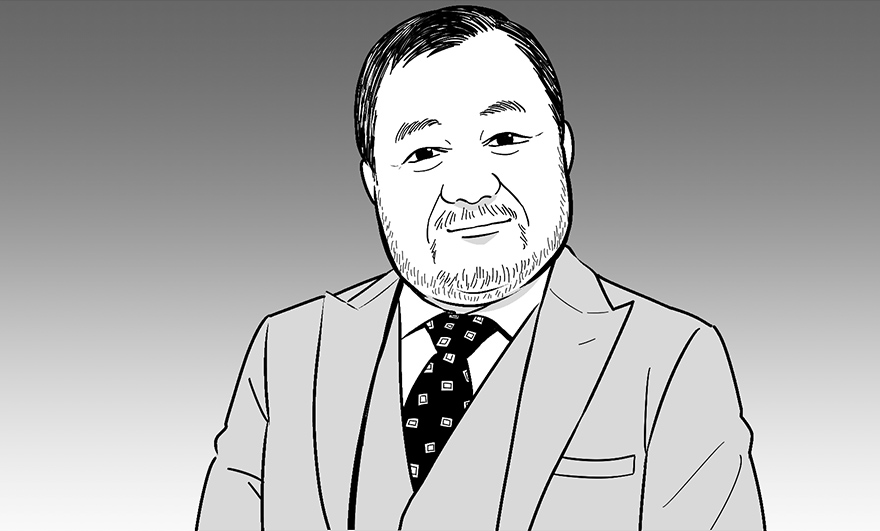
1946年、京都市生まれ。作家、作詞家、編集者としてテレビや雑誌など多くのメディアで活躍。1968年、ザ・フォーク・クルセダーズの友人、加藤和彦や北山修と共に作った『帰ってきたヨッパライ』がミリオンセラー・レコードとなる。1970年代、平凡出版(現マガジンハウス)の『ポパイ』『ブルータス』などの創刊に関わる。70年代から機械式時計の世界に魅せられ、スイスへの取材を通じ、時計の魅力を伝える。著書に映画『パッチギ!』の原案となった自伝的小説『少年Mのイムジン河』のほか、『松山猛の時計王』『それでも時は止まらない』、遊びシリーズ『ちゃあい』『おろろじ』など。
原点時計はグリュエンのトノー型アンティークウォッチ
Q. 最初に手にした腕時計について教えてください。
A. 僕が初めて腕時計を手にしたのは、少し遅くて24歳ぐらいのことでした。京都公立の芸術高校に通っていた頃は「時間なんかに縛られてたまるものか」と粋がっていたんですね。それに子供の頃に暮らしていた京都では星空が澄んでよく見えたから、時計代わりに星を見ていました。東山の小路あたりを見上げると、羊羹みたいな細い空にオリオン座やカシオペア座などが横切っていて、そうするとだいたい正確な時間が分かったんですね。
時計との出合いは、東京に引っ越して、社会に出てからのことでした。知り合いのスタイリストさんが持っていたカルティエのタンクを見たことがきっかけです。僕はそれまで丸型の腕時計しか知らなかったから角型は新鮮でしたし、その素晴らしい存在感に憧れましたね。ただ、僕にはまだ高級時計を買う資力はありませんでした。そんなある日、アメリカへ行く機会があって、現地のフリーマーケットで見付けたのがトノーシェイプのグリュエンの腕時計でした。金張りケースの並品で、当時の僕の暮らしぶりにはちょうど良い感じだったし、ハンフリー・ボガートが着けていそうな佇まいも気に入りました。購入後は毎日着けていましたよ。この時計のムーブメントを修理店で初めて見たことも、時計への興味が高まったきっかけのひとつでした。このグリュエンの腕時計が僕の原点時計ですね、今も大切にしています。

「上がり」時計は、F.P.ジュルヌ「アストロノミック・スヴラン」
Q.いつしか手にしたいと願う憧れの時計、いわゆる「上がり時計」について教えてください。
A. この質問には困ったなぁ。まだまだ欲しい時計はたくさんあるわけですからね。でも今回は、もし僕が億万長者になれたならと想像して考えてみました。F.P.ジュルヌの「アストロノミック・スヴラン」ですね。4年くらい前にジュネーブ・ウォッチメイキング・グランプリの審査員としてジュネーブへ行ったとき、実はフランソワ-ポール・ジュルヌ本人から新しい天文時計を作る予定だと教えてもらっていて、それからずっと完成を楽しみにしてきました。いざ出来上がった時計を目にしたときには、これだけ複雑な機能をよくここまで小型化できたものだと驚かされましたね。素晴らしい時計師は多くいますが、今、僕がいちばん尊敬しているのはジュルヌです。デザイン性がぶれないところも好きですね。彼が初期に限定品として出した、プラチナ製のデイ&ナイト(オクタ・ジュール/ニュイ)は手に入れて大事にしていますよ。アストロノミック・スヴランは、手が届かないなぁ。宝くじが当たったら絶対に買うんだけれどね。

あとがき
作家・作詞家として活躍し、時計に関する研究、執筆も多く手掛けられた松山猛さん。機械式時計ブーム初期の立役者となられたおひとりだ。松山さんの著書に、次の一文がある。クォーツ時計が市場を席巻した1980年代当時の心境を綴った言葉だ。「人間が何百年もかけて築き上げてきた、ゼンマイと歯車だけによる、極めて精密な、時を計るメカニズムが、このまま忘れられてはならない。クォーツ以降も、時計は進化を続けるだろうが、その基本を作った機械式の魅力を、僕たちの時代で捨て去るなど、とんでもないことではないか」(『それでも時は止まらない』/世界文化社)。何百年分の叡智の結晶は、儚く失われる危うさも、進化を続ける強かさもどちらも併せ持っている。多くのメディアで機械式時計の楽しさを伝えてきた松山さん、根底にはこんな思いもあったのだ。